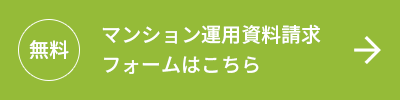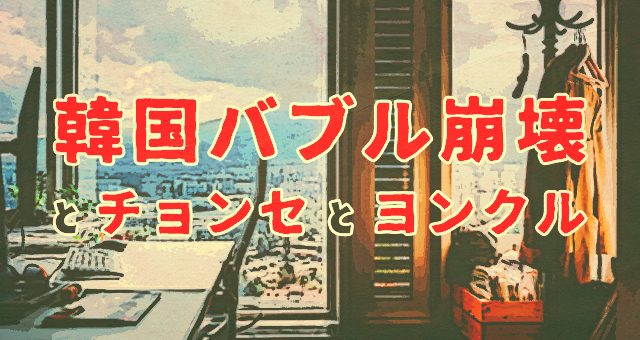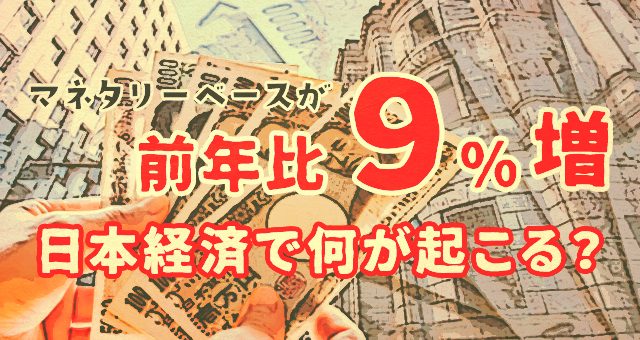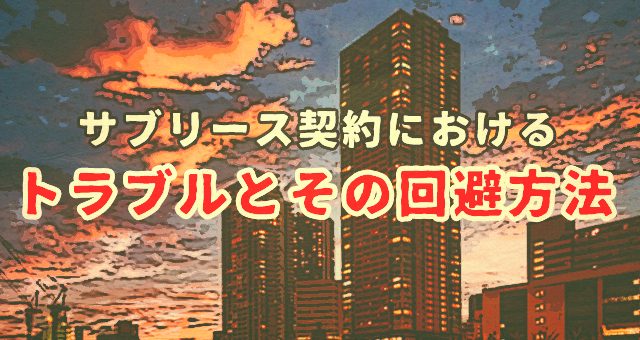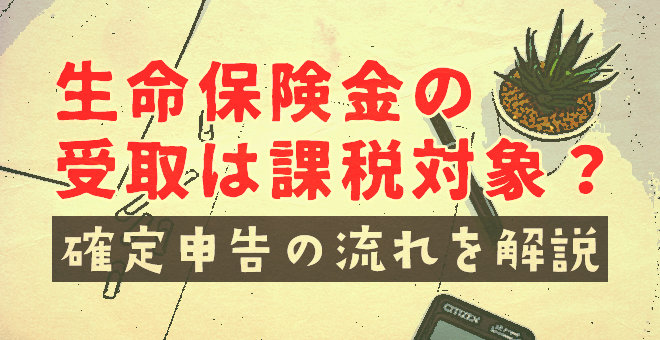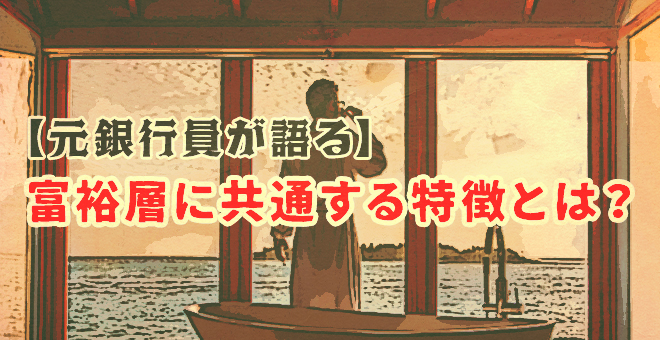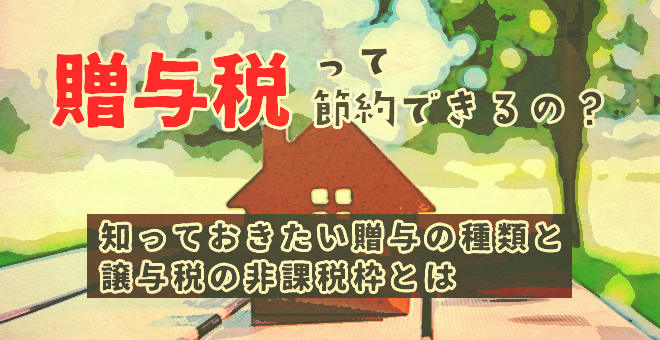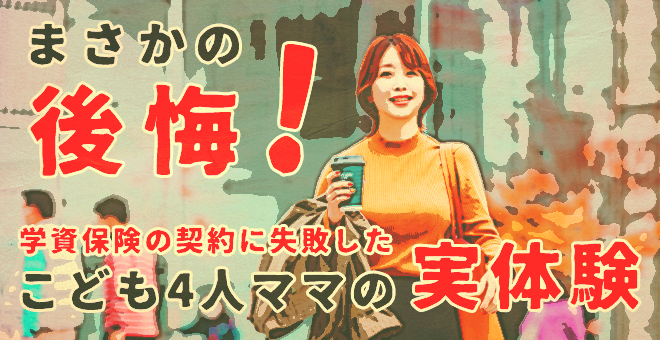ニトウコラム
日本の平均年収は458万円!男女別・雇用形態別の年収を解説

2023年9月27日、国税庁より「令和4年分民間給与実態統計調査結果」が公表されました。この調査によると、日本の平均年収は458万円となっています。
この金額を多いと見るか少ないと見るかは個人差がありますが、男女別や年代別の平均年収をみると少し実態が変わってきます。本記事では、日本の平均年収をさまざまなデータ別で解説していきます。
目次
1.日本の平均年収は?
国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査結果」によると、2022年における日本の平均年収は458万円です。前年調査の平均年収は446万円でしたので、12万円増加した結果となりました。
上記グラフは、日本の平均年収の推移を示したものです。コロナ禍では減少に転じたことがあるものの、2022年は400万円台後半に突入したことから、順調に年収が増加していることが分かります。
しかし、角度を変えて調査結果を見てみると、その実態は少し変わってきます。ここからは、男女別や年代別などデータ別の平均給与を確認していきましょう。
1-1.男女別
まずは、男女別の平均年収についてです。
国税庁の同調査によると、男性の平均年収は563万円である一方、女性は313万円となっており、大きな差があることが分かります。女性の中には、結婚や出産などのライフステージの変化によって、パートタイム労働として働くことを選択する人も多いことから、男女の平均年収に差が出る結果となりました。
とはいえ、近年の平均年収の推移を見てみると、女性の方が伸び率が大きいことが分かります。
| 調査年 | 女性 | 男性 | ||
| 平均年収(千円) | 前年対比(%) | 平均年収(千円) | 前年対比(%) | |
| 平成26年 | 2,738 | – | 4,209 | – |
| 27年 | 2,758 | 0.7 | 4,234 | 0.6 |
| 28年 | 2,802 | 1.6 | 4,250 | 0.4 |
| 29年 | 2,875 | 2.6 | 4,336 | 2.0 |
| 30年 | 2,930 | 1.9 | 4,391 | 1.3 |
| 令和元年 | 2,960 | 1.0 | 4,384 | -0.2 |
| 2年 | 2,929 | -1.0 | 4,351 | -0.8 |
| 3年 | 3,018 | 3.0 | 4,457 | 2.4 |
| 4年 | 3,137 | 3.9 | 4,576 | 2.7 |
現在は、政府も女性の社会進出を後押ししていることから、将来的には男女の差が埋まってくることもあるかもしれません。
1-2.年代別
下記表は、国税庁の同調査から年代別の平均年収をまとめたものです。
| 年代 | 平均年収 |
| 19歳以下 | 124万円 |
| 20~24歳 | 273万円 |
| 25~29歳 | 389万円 |
| 30~34歳 | 425万円 |
| 35~39歳 | 462万円 |
| 40~44歳 | 491万円 |
| 45~49歳 | 521万円 |
| 50~54歳 | 537万円 |
| 55~59歳 | 546万円 |
| 60~64歳 | 441万円 |
| 65~69歳 | 342万円 |
| 70歳以上 | 298万円 |
年代別の平均年収をみると、年齢とともに平均年収が増加していることが分かります。
最も平均年収が高くなるのは55~59歳の546万円で、定年退職を迎える60歳以降は徐々に年収が減少している状況です。
1-3.雇用形態別
国税庁の同調査では、雇用形態別の平均年収も調査されており、正社員の平均年収は523万円である一方、正社員以外の平均年収は201万円と大きく差があることが分かります。
さらに、これを男女別で見てみましょう。
| 正社員 | 正社員以外 | |
| 男性 | 584万円 | 270万円 |
| 女性 | 407万円 | 166万円 |
男女どちらも雇用形態によって大きく差があり、特に女性については正社員以外の平均年収が200万円を切る状況です。全体の平均年収は458万円であるものの、その実態は性別や働き方によって大きく違うといえるでしょう。
1-4.業種別
平均年収は業種によっても異なります。下記の表で確認してみましょう。
| 業種 | 平均年収 |
| 建設業 | 529万円 |
| 製造業 | 533万円 |
| 卸売業・小売業 | 384万円 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 268万円 |
| 金融業・保険業 | 656万円 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 457万円 |
| 運輸業・郵便業 | 477万円 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 747万円 |
| 情報通信業 | 632万円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業 | 544万円 |
| 医療・福祉 | 409万円 |
| 複合サービス事業 | 506万円 |
| サービス業 | 377万円 |
| 農林水産・鉱業 | 337万円 |
最も平均年収が高いのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」で747万円となっています。次いで「金融業・保険業」が656万円、情報通信業が632万円で、全体の平均年収と比べても高収入であることが分かります。
一方、最も平均年収が低いのは「宿泊業・飲食サービス業」で268万円です。
2.最も割合が多いゾーンは300万超~400万円
ここまで、さまざまなデータ別で平均年収をみると、性別や雇用形態、業種などによって大きく平均年収が異なることが分かりました。そのため、全体の平均年収である458万円は、一部の高収入の人によって引き上げられているともいえるでしょう。
では実際のところ、日本ではどれくらいの給与階層の人が多いのでしょうか。下記表は、給与階層別の構成割合を示したものです。
| 給与階層 | 構成割合(%) |
| 100万円以下 | 7.8 |
| 100万円超200万円以下 | 12.7 |
| 200万円超300万円以下 | 14.1 |
| 300万円超400万円以下 | 16.5 |
| 400万円超500万円以下 | 15.3 |
| 500万円超600万円以下 | 10.9 |
| 600万円超700万円以下 | 6.9 |
| 700万円超800万円以下 | 4.8 |
| 800万円超900万円以下 | 3.3 |
| 900万円超1,000万円以下 | 2.2 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 4.0 |
| 1,500万円超2,000万円以下 | 0.8 |
| 2,000万円超2,500万円以下 | 0.3 |
| 2,500万円超 | 0.3 |
最も構成割合が多いのは、「300万円~400万円超」のゾーンで全体の16.5%が分布している結果となりました。年収が400万円以下の人の割合は合計で51.1%となり、およそ半数の人が平均年収以下となる状況です。
3.年収アップのために取り組みたいこと

日本の平均年収をみて、「もっと年収アップを狙いたい」と感じた人もいるかもしれません。年収を増やすためには、どのようなことに取り組めば良いのでしょうか。主な方法として、次の4つが挙げられます。
| ・平均年収が高い業界への転職 ・資格取得でキャリアアップ ・副業で毎月の収入アップ ・コツコツと配当株を増やす |
それぞれくわしく解説していきましょう。
3-1.平均年収が高い業界への転職
先ほど、業種別の平均年収で紹介した通り、年収アップを狙うためには「どの業界で働くか」ということも大切なポイントです。一般的にインフラ業界や金融業界、IT業界は年収が高い傾向にあり、思い切ってキャリアチェンジを検討してみるのもよいでしょう。
しかし、当然ながら年収アップだけを目的とした転職はおすすめできません。「その業界でどんな仕事がしたいか」というキャリアプランをしっかりと立てたうえで転職活動に取り組むことが大切です。
3-2.資格取得でキャリアアップ
年収アップには、仕事に活かせる資格を取得することも有効です。たとえば、企業によっては資格を取得することによって、資格手当を受け取れるケースもあります。
また、資格を取得することで昇進し、給与が上がることもあるかもしれません。
自分が勤める企業の就業規則や賃金規定などを確認し、業務や年収アップに役立てられる資格はないかチェックしてみましょう。
3-3.副業で毎月の収入アップ
最近は、従業員の副業を認める企業が増えてきました。金融業界や公務員など副業禁止とされてきた職種でも解禁の流れが出ており、「土日に副業をしている」という人も珍しくありません。
たとえば、毎月5万円副業で収入が得られたら、年間60万円もの収入アップにつながります。中には、在宅でできる副業もありますので、自分に合うものがないか探してみましょう。
3-4.コツコツと配当株を増やす
投資によって収入を増やす方法もあります。株式の中には、定期的に配当金を出す銘柄があり、配当金の受け取りを楽しみに投資に取り組む人も少なくありません。
また、NISA口座で買いつければ配当金にかかる税金もかからないため、より効率よく利回りを得られるメリットもあります。
ただし、一気に配当銘柄へ投資することはおすすめできません。リスクを分散するためにも、購入するタイミングをずらしながらコツコツと買い増していきましょう。
4.支出の削減も大切
収入アップに取り組む一方、支出を減らす工夫をすることも大切です。ここでは、節約と節税について考えてみましょう。
4-1.毎月の固定費削減
毎月の支出を減らすためには、家計の見直しから行う必要があります。きちんと家計簿をつけてみれば、「ここはもう少し削減できそうだな」という支出が見つかったりするものです。
通信費や光熱費、食費など、かさんでいる支出はないかよく振り返ってみましょう。
4-2.節税対策
支出を減らすためには、節税対策も有効です。会社員の場合は、住民税や所得税が給与から天引きされているため、どれくらいの税金を納めているかピンとこない人も多いかもしれません。
たとえば、年収400万円の人は所得税が20%、住民税が10%なので、年収のおよそ30%が税金で差し引かれます。
少しでも税負担を和らげるためには、iDeCoや生命保険、医療費控除などを活用することもおすすめです。
5.まとめ
2022年における日本の平均年収は458万円ですが、これは一部の高所得の人が平均額に影響を与えており、実際は約半数の人が平均年収以下となる状況です。年収アップを狙うためには、転職や資格取得、副業などに取り組むことを検討してみましょう。
また、収入を増やすだけでなく、節約や節税など支出を減らすことも大切なポイントです。
【参考】
国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査結果」
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2022/pdf/002.pdf