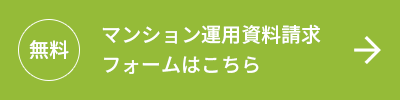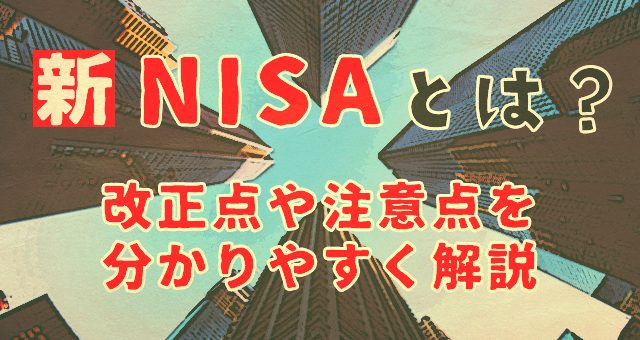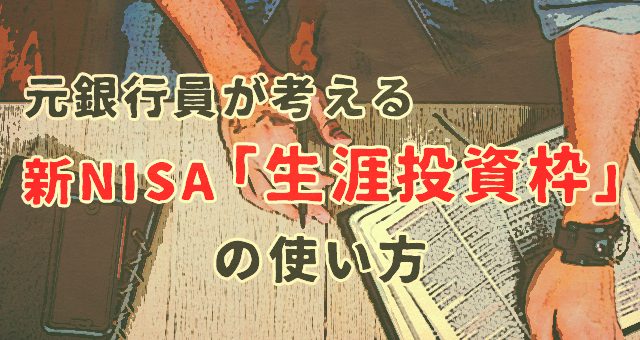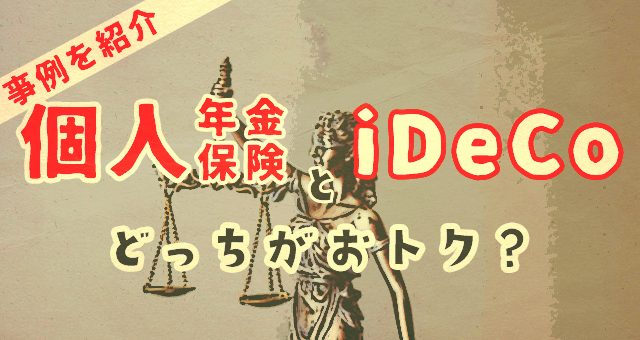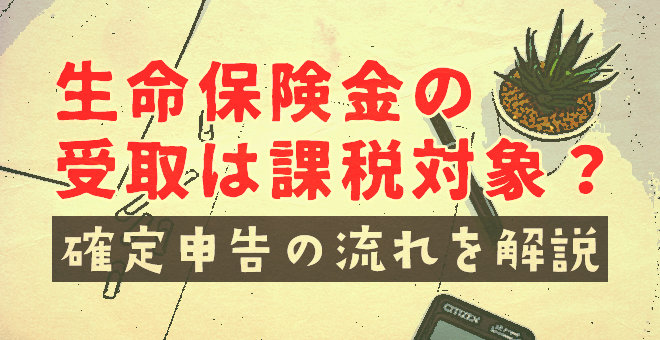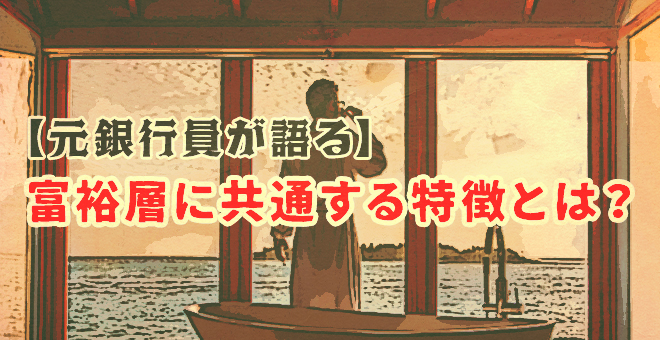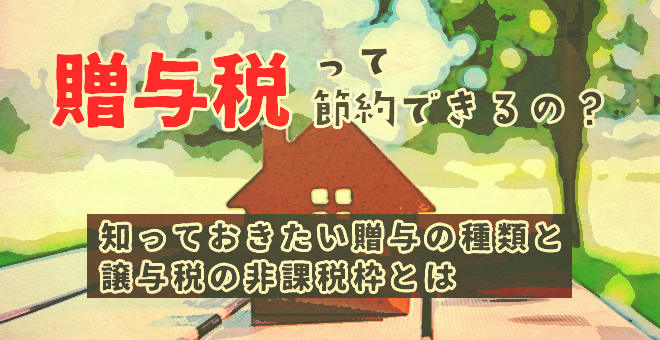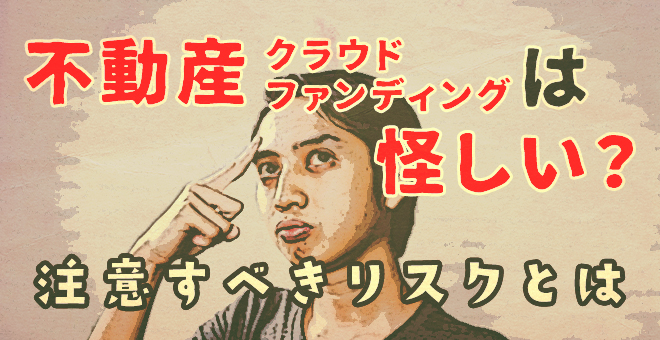ニトウコラム
【元銀行員が解説】NISAとiDeCoどっちから始めるべき?
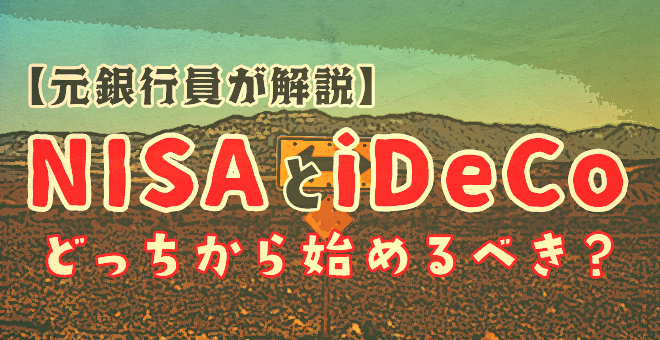
資産形成を支援する制度の「NISA」と「iDeCo」。どちらも税制優遇を受けられることが特徴ですが、「どっちを使った方がいいのだろう」、「自分に向いている制度が分からない」と悩んでいる人もいるかもしれません。
本記事では、2024年から始まる新しいNISAとiDeCoの違いを押さえたうえで、それぞれおすすめの人について解説していきます。
目次
1.新しいNISAとiDeCoの違い
NISAとiDeCoの制度の主な違いについて、下記の表にまとめています。
| 新しいNISA | iDeCo | ||
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | ||
| 対象年齢 | 18歳以上 | 20~60歳 | |
| 非課税期間 | 無期限 | 受け取り開始まで | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 職業によって異なる |
| 非課税保有限度 | 1,800万円(内、成長投資枠については1,200万円まで) | なし | |
| 引き出し制限 | なし | 原則60歳まで引き出し不可 | |
| 運用商品 | 金融庁の定める基準をクリアした投資信託・ETF | 上場株式 投資信託、ETF ※一部対象外銘柄あり |
定期預金 投資信託 |
まずは、主な違いをひとつずつ学んでいきましょう。
違い①運用商品
新しいNISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠が設けられており、それぞれ対象となる運用商品が異なります。
| 投資枠 | 運用商品 |
| つみたて投資枠 | 金融庁の定める基準をクリアした投資信託・ETF |
| 成長投資枠 | 上場株式 投資信託、ETF ※一部対象外銘柄あり |
(※①整理・監理銘柄、②信託期間が20年未満、毎月分配型、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託は除外)
つみたて投資枠では金融庁による基準が設けられているものの、成長投資枠では上場株式にも投資できるようになっており、幅広い対象の中から投資先を選定できます。
一方、iDeCoは定期預金や投資信託が運用対象です。その選択肢の数は金融機関によって異なりますが、最大でも35商品となっています。
違い②非課税期間
現行のNISAでは、つみたてNISAが最大20年間、一般NISAが最大5年間と非課税期間が設けられていましたが、新しいNISAでは非課税期間が無期限化されます。そのため、生涯非課税で投資することも可能です。
一方、iDeCoは年金の受取開始が60歳ですので、それまで非課税で運用することができます。
2024年以降はどちらも長期間非課税で運用できることから、非課税期間についてはあまり大きな差はないといえます。
違い③運用金額
新しいNISAの年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円となり最大360万円非課税での投資が可能です。また、1人あたりが非課税で投資できる「生涯投資枠」は1,800万円となっています(成長投資枠はその内1,200万円まで)。
一方、iDeCoでは職業によって拠出上限額が設けられており、詳細は下記の通りです。
| 加入者区分 | 拠出限度額 | |
| 第1号被保険者(自営業者など) | 月額6万8,000円 | |
| 第2号被保険者(会社員・公務員など) | 会社に企業年金がない人 | 月額2万3,000円 |
| 企業型DCのみ加入している人 | 月額2万円 | |
| ・DBと企業型DCに加入している人 ・DBのみ加入している人 ・公務員 |
月額1万2,000円 | |
| 第3号被保険者(専業主婦・主夫など) | 月額2万3,000円 | |
iDeCoに加入する際は、自分はどの限度額に該当するかチェックしておきましょう。
違い④手数料
資産運用に取り組む際は、手数料について比較することも大切なポイントです。
NISAでの手数料は、運用する商品によって発生するコストが異なります。
| 運用商品 | 手数料 |
| 上場株式 | 売買手数料 |
| 投資信託 | ・購入手数料 ・信託報酬 ・信託財産留保額 |
また、これらの手数料は利用する証券会社やファンドによって異なります。どの証券会社を利用するか、どのファンドに投資するかということを選定するときは、必ずコストについても比較しましょう。
一方、iDeCoでは次のような手数料がかかります。
| 手数料金額 | |
| 加入・移換時手数料(初回1回のみ) | 2,829円 |
| 加入者手数料(掛金納付の都度) | 105円 |
| 運営管理手数料 | 金融機関によって異なる |
また、iDeCoでは投資信託で掛金を運用する場合であっても、購入手数料がかかりません。ただし、信託報酬や信託財産留保額についてはNISAと同様に発生しますので、各ファンドのコストをしっかりと確認しましょう。
違い⑤引き出し制限
NISAとiDeCoの最も大きな違いが「引き出し制限」です。
NISAはいつでも保有資産を売却して現金化できますが、iDeCoでは原則60歳まで引き出しができません。一部中途解約が認められるケースはあるものの、「国民年金保険料を免除されている場合」など限定的となっています。
特に、20代や30代などの若年層は、60歳まで資金が拘束されることに抵抗がある人もいるかもしれません。NISAとiDeCoを比較する際は、引き出し制限についてよく理解しておきましょう。
違い⑥税制優遇
NISAとiDeCoはどちらも税制優遇を受けられる制度ですが、どのような場面で税制優遇が受けられるかが大きく異なります。
NISAで税制優遇が受けられるのは、「資産を売却したとき」や「分配金・配当金を受け取ったとき」です。株式や投資信託の運用で得た利益には、本来20.315%の税金が課税されますが、NISAではこの税金が非課税となり、利益をそのまま受け取ることができます。
一方、iDeCoで税制優遇が受けられるのは、次の3つのシーンです。
| ①掛金を拠出するとき ②掛金の運用で利益が出たとき ③掛金を受け取るとき |
特に現役世代にとってメリットが大きいのは、掛金の拠出に対する税制優遇です。iDeCoでは掛金が全額所得控除されるため、現在納めている住民税や所得税の負担が軽減される効果があります。
iDeCoの税制優遇については、記事内でくわしくシミュレーションしていますので、そちらも併せて参考にしてみてください。

2.節税効果を重視するならiDeCoがおすすめ
ここまで紹介したNISAとiDeCoの違いを踏まえたうえで、それぞれの制度がおすすめの人を解説していきましょう。
iDeCoがおすすめの人は、次のような意向がある人です。
| ・節税対策に取り組みたい人 ・老後の生活資金を貯めたい人 |
特に、iDeCoはNISAと比べて税制優遇が充実している制度ですので、「資産形成をしながら節税対策をしたい」という人にはピッタリの制度です。実際にiDeCoの利用によって、どれくらいの税負担を軽減できるのかシミュレーションしてみましょう。
2-1.税制優遇シミュレーション
前述の通り、iDeCoは掛金を全額所得控除できる制度です。具体的にどれくらいの税負担が軽減できるのか試算してみましょう。
| 【前提条件】 ・課税所得400万円 ・iDeCoに毎月2万円拠出 |
このケースでは毎月2万円を拠出できますので、合計24万円を所得から控除することができます。よって、iDeCo加入により軽減できる税負担は下記の通りです。
| 【所得税】4万8,000円 【住民税】2万4,000円 【合計】7万2,000円 |
年間7万円もの税負担を軽減できるのは、大きな魅力ではないでしょうか。
2-2.無理のない金額で取り組むことが大切
先ほどの税制優遇シミュレーションを見ると、「税負担を軽減するために、上限ギリギリまで掛金を拠出したい」と感じる人もいるかもしれません。しかし、iDeCoは原則60歳まで引き出しができないため、掛金は慎重に設定する必要があります。
もし「急な出費が重なって手持ちの現金では足りない」ということがあっても、iDeCoに拠出した資金は引き出しができません。無理に上限いっぱいまで拠出するのではなく、長期間運用に回せる余裕資金で取り組むようにしましょう。
3.少額投資ならNISAがおすすめ

一方、NISAが向いているのは次のような意向がある人です。
| ・上場株式に投資したい人 ・少額投資から始めたい人 |
投資信託の最低投資金額は証券会社によっても異なりますが、中にはワンコインから始められるところもあります。資産の売却もいつでもできますので、「まずは、気軽に資産運用を始めてみたい」という人はNISAの方がハードルが低いでしょう。
3-1.少額投資の運用シミュレーション
NISAは少額投資から始められることが魅力の制度です。ここでは、毎月1万円を積立投資した場合の運用成果をシミュレーションしてみましょう。
【毎月1万円を年利5%で運用したとき】
| 運用期間 | 投資元本 | 運用成果 |
| 10年 | 120万円 | 155万2,823円 |
| 15年 | 180万円 | 267万2,889円 |
| 20年 | 240万円 | 411万337円 |
| 25年 | 300万円 | 595万5,097円 |
仮に年利5%の運用が続けられると、毎月1万円の積立でも25年後には約600万円の資産になっています。
しかも、新しいNISAでは生涯非課税が適用されますので、25年後に売却したときも利益分の約300万円に税金が課されることはありません。まずは、無理のない金額からコツコツと積立投資を始めてみましょう。
3-2.リスクテイクは適切に
NISAは、上場株式や投資信託、ETFなどさまざまな金融商品が投資対象となっています。「早く資産を増やしたい」という気持ちがあると、値動きの大きい商品をメインに投資したくなるかもしれません。
しかし、投資先を選定するときは損失を抱えるリスクについてよく考えることが大切です。「どれくらいの損失に耐えられるか」、「運用期間は何年間あるか」といったことを考慮しながら、適切なリスクテイクとなるように心がけましょう。
5.資産形成は税制優遇を活用しよう
NISAとiDeCoは、どちらも資産形成をしながら税制優遇を受けられる制度です。しかし、運用金額や対象商品などが異なるため、その特徴を理解して自分に合った制度を選ぶことが大切です。
また、NISAとiDeCoは併用することもできます。収支に余裕がある場合は、NISAとiDeCoを併用することも検討してみるとよいでしょう。