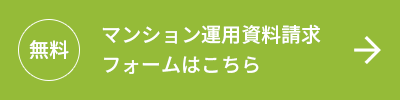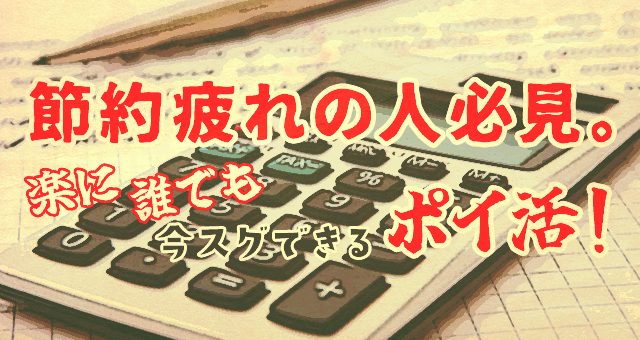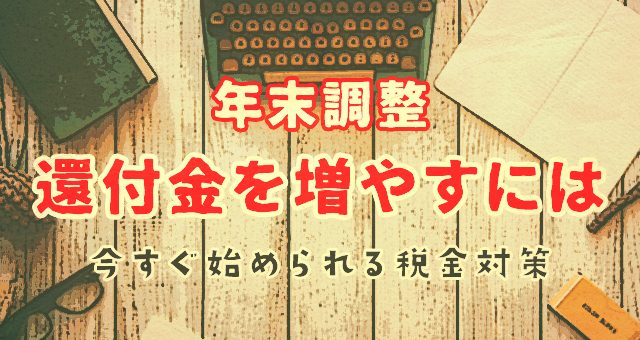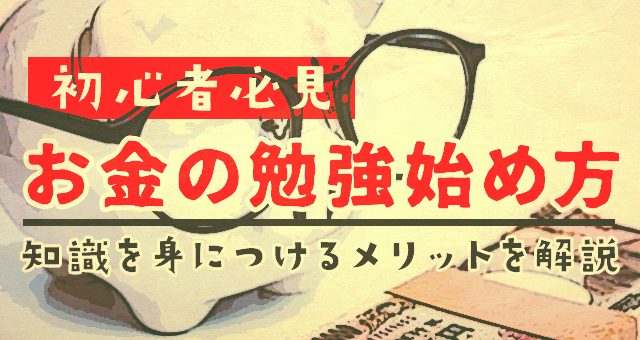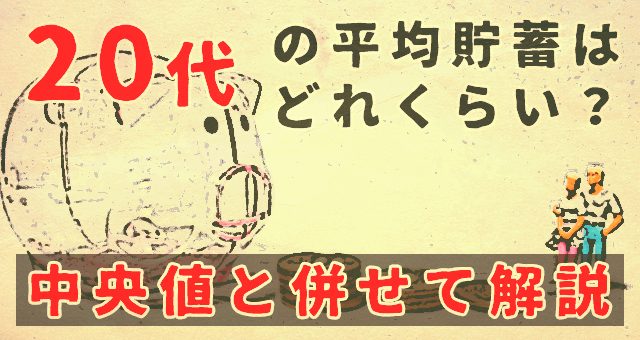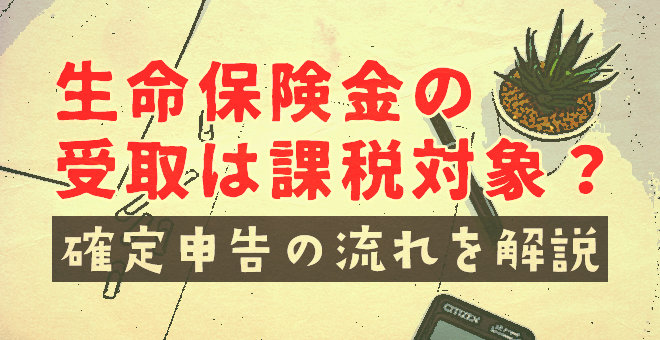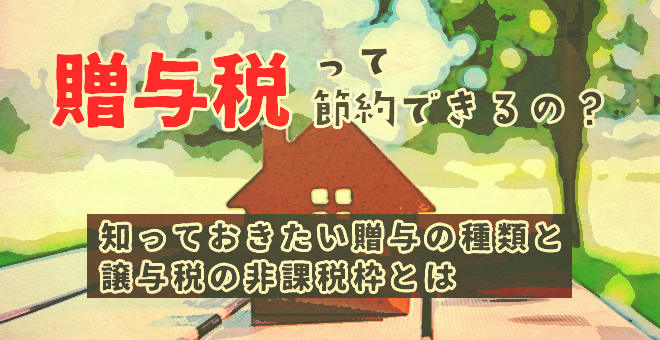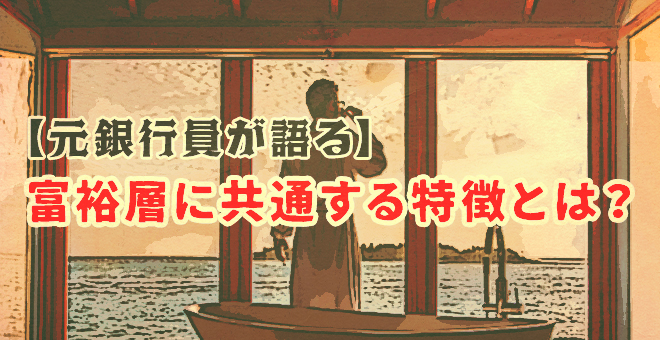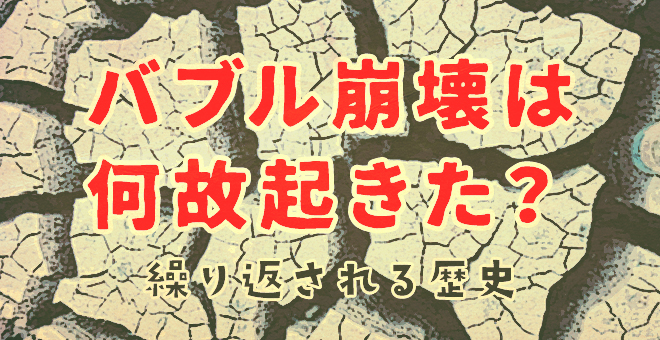ニトウコラム
出費から読み解く!1年でもっともお金のかかる時期はいつ?
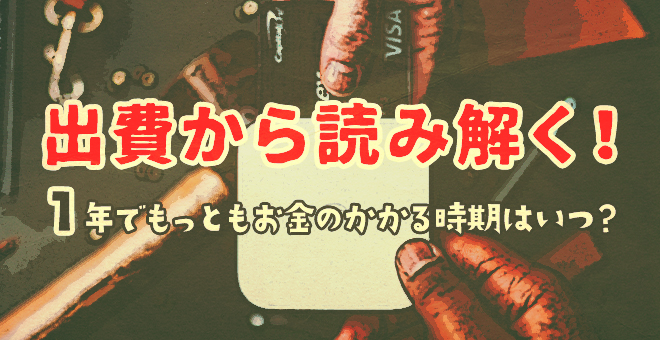
わが国では、ウクライナ侵攻の影響を受け世界的な燃料価格の高騰や円安等が原因で電気料金が値上げしています。大手電力7社は、料金改定の申請を行い、2023年6月より新規性料金(値上げ)が適用されています。
出典:※1
物価高などもあり、各家庭の出費は死活問題ともいえるでしょう。食料価格が高騰して、電気代まで値上がりすれば、生活水準や生活嗜好(しこう)も見直さなければなりません。
それには、年間を通じていつ頃の時期に出費が増えるのか、を知っておくことも大事です。この記事では、1年でもっともお金(出費)のかかる時期はいつなのか?について解説します。出費に対してどのような節約効果が期待できるかなどもあわせて紹介します。
目次
1年でもっとも出費が多い時期とは
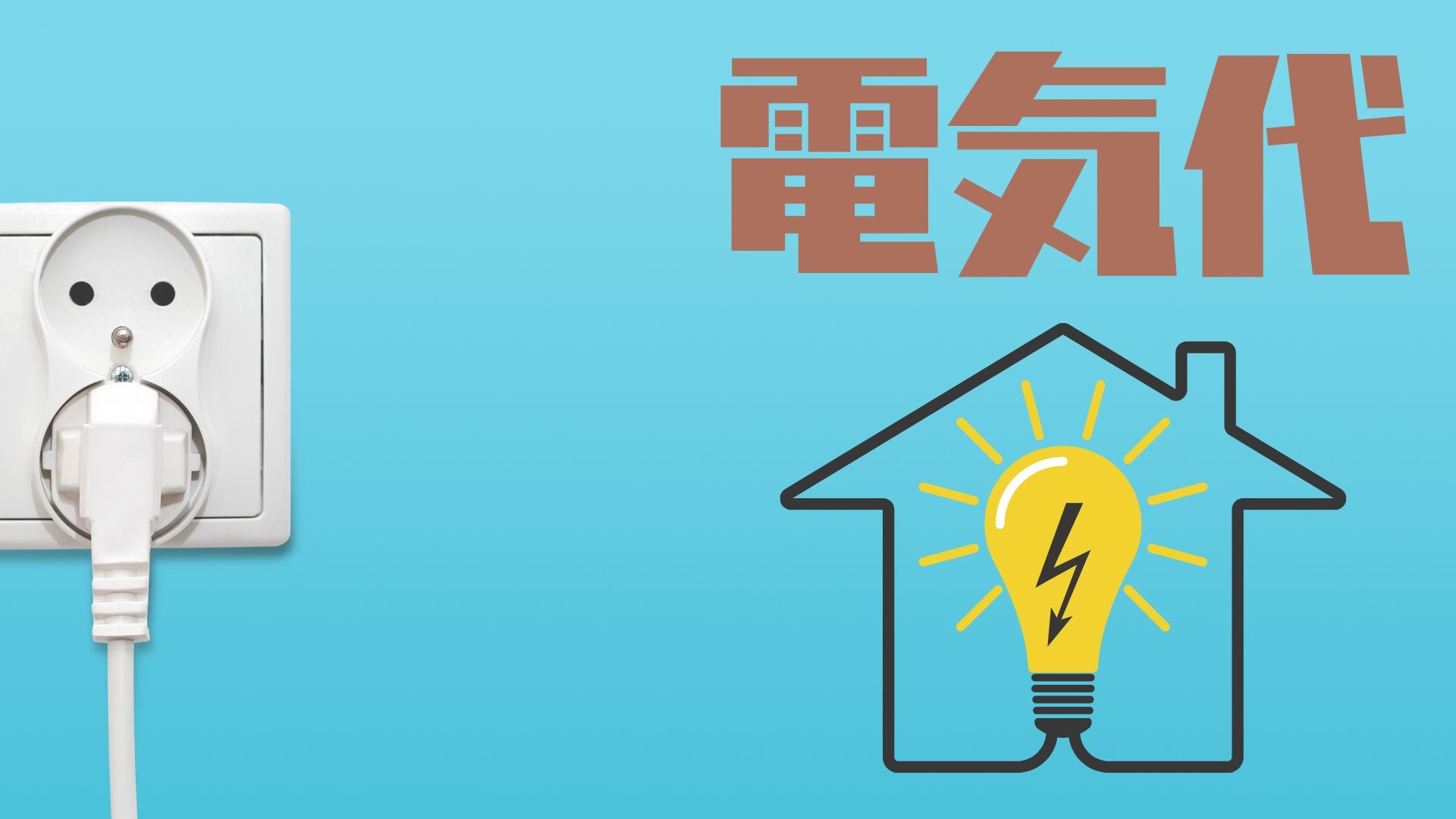
消費者庁の調べによると、1年でもっとも出費の多い時期は、12月という結果が出ています。調査対象となったのは二人以上の世帯における家計調査です。2019年と2020年のコロナ前とコロナ禍の消費支出の推移からどちらの年も12月の消費支出が最も多くなっています。
総務省「家計調査」、「2人以上の世帯」における1世帯当たりの消費支出の推移(単位:円)
| 2019年 | 2020年 | |
| 1月 | 296,345 | 287,173 |
| 2月 | 271,232 | 271,735 |
| 3月 | 309,274 | 292,214 |
| 4月 | 301,136 | 267,922 |
| 5月 | 300,901 | 252,017 |
| 6月 | 276,882 | 273,699 |
| 7月 | 288,026 | 266,897 |
| 8月 | 296,327 | 276,360 |
| 9月 | 300,609 | 269,863 |
| 10月 | 279,671 | 283,508 |
| 11月 | 278,765 | 278,718 |
| 12月 | 321,380 | 315,007 |
出典:消費者庁「令和3年版消費者白書|第1部第2章第1節(1)消費の動向|図表1-2-1-2消費支出の推移」をもとに作成
もっとも出費の多い12月
12月は、忘年会やクリスマス、大みそかなど1年を締めくくるイベントが盛りだくさんです。前項での消費支出推移からも12月がもっとも支出の多い月と判断できます。総務省の公開している「年末年始の消費支出」では、世帯当たりの1カ月間の月別消費支出金額(2022年実施)が示されています。
2022年の同資料では、年平均の支出金額が29万円のところ、同年12月の支出金額は32万7000円ともっとも多い月に該当します。2022年12月の消費支出は、年平均の1.13倍という結果です。
データ参照:※2
たとえば、クリスマスプレゼントの購入や正月用品の購入なども重なることも支出の増える要因として考えられます。
1年でもっとも電気代が高い時期とは
エネルギーテック企業のENECHANGE株式会社は、総務省統計局の「家計調査」による冬と年間の平均電気代の差を公開しています。
| 総務省統計局2022年家計調査による平均電気代(単位:円) | ||
| 冬の平均電気代
(2022年1月~3月の平均) |
1人暮らし | 7,740 |
| 2人暮らし | 13,216 | |
| 3人暮らし | 15,320 | |
| 4人暮らし | 16,286 | |
| 5人暮らし | 18,467 | |
| 年間通した平均電気代
(2021年1月~12月の平均) |
1人暮らし | 5,482 |
| 2人暮らし | 9,183 | |
| 3人暮らし | 10,655 | |
| 4人暮らし | 11,376 | |
| 5人暮らし | 12,423 | |
出典:ENECHANGE株式会社「エネチェンジ|冬の平均的な電気代は?冬の電気代が高い理由と節約方法」掲載の総務省統計局データをもとに作成
上記の平均電気代から、家庭の人数に関係なく年間平均よりも冬の電気代が高いと判断できます。そのため、地域の違いも含めて考えると1年でもっとも電気代が高い月は、1月〜3月となるでしょう。
節約につながる行動

出費を抑えるためには、必要以上の使用を控えるしかありません。もしくは、必要以上に電気代や燃料を使う機械や設備の見直しなども考えられます。では、節約につながる行動はどのようなものがあるのでしょうか。
出費を抑えるために節約したいこと
消費者庁の公開している全国の18歳〜69歳までの男女を対象にした「今後の生活に関するアンケート(2017年実施)」では、支出を減らしたい項目として次の結果となっています。
- 水道光熱費:30.3%
- 外食費:29.3%
- 食費(外食費を除く):25.8%
- 通信費:25.6%
- とくにない:20.5%
- 衣料費:16.5%
- 医療費:12.3%
出典:※4 図表4のデータをもとに作成
もっとも支出を減らしたいと考えている出費は、「水道光熱費」です。逆に支出を増やしたい項目でもっとも多かったのが、「貯蓄など財産づくり」で全体の41.3%となっています。
減らしたい支出の項目「水道光熱費」は、40代〜60代の女性の意見を反映しています。2017年時点の同資料では、景気が回復したとしても個人消費行動は活発にならないと判断しています。多様化が進む現代では、モノへの執着よりも「他者・環境への配慮」の意識が強まることを指摘しています。
参考:※4
そのように考えると、光熱費を抑えてその分、お金を蓄えるという判断になります。節約するには、電気代や水道代への対策が必要なのでしょうか。
電気代で節約できること
2023年6月より値上がりしている電気代に対して、政府広報オンラインが公開している節約(節電)のポイントを参考にしてみましょう。当たり前のようで知らなかった方法があれば、試してみてはいかがでしょうか。
エアコンの使い方で節電
政府広報オンラインでは、窓や扉の開口部をカーテンなどで閉じることが節電になると指摘しています。カーテンは、日差しだけではなく野外の熱気も遮断するからです。とくに効果が高いのは、厚手の遮熱カーテンだと伝えています。
また、2週間に一度のエアコンのフィルター清掃や室外機の周囲にモノを置かないことなども指摘しています。
参考:※5
冷蔵庫の使い方で節電
政府広報オンラインでは、冷蔵庫の節電について以下の行動を取り上げています。
- 冷蔵庫の設定温度の変更:「強」から「中」へ
- 冷蔵庫内のスペース:冷蔵庫内に食材を詰め込み過ぎない
- 庫内の温度を上げない工夫:熱いものは冷ましてから入れる
- 冷蔵庫自体の設置:背面や側面0.5cm~2cm、上部5~30㎝以上の放熱スペースを確保する
参考:※5
食品ロスの減少も節約効果を期待できる
消費者庁では、節約方法として食品ロスの減少を呼びかけています。物価高は、日常の食材にも影響を呼び、原材料価格の高騰から、さまざまな商品が値上がりしています。そのような状況でも、買いだめや衝動買いなどで予定外の商品を買ってしまうことはよくある話です。
そこで消費者庁では、食品ロスを出さないためのアイデアを以下のように伝えています。
- 家にある食材や食品のチェック:冷蔵庫・冷凍庫・食品棚・床下収納など
- 必要な食材のメモを取る:手書きメモやスマホメモ、ホワイトボードのキャプチャなど
- 使い切れる分だけ購入する:食べきれずに捨てないことを念頭に判断する
- 買い物を避けた方が良い状態:空腹時やイライラしているとき(余計に買ってしまう)
- 買った野菜の最適な保存管理:常温・冷蔵(野菜室)・冷凍
- 買った肉・魚の最適な保存管理:余計な水分の除去・下味処理後の冷凍など
最近では、NPO法人によるフードバンクの活用も注目されています。食べきれない食材などをフードバンクに寄付する活動です。
参照:※6
身近な節約といえば、生活家電の節電や食品ロスの削減などが取り組みやすい方法と考えられます。ただし、節約の効果は積み重ねによるものであって、いきなり大きな効果を期待できません。
節約しておけば、節約しないよりは成果があるという程度に考えておきましょう。
節約だけではなく資本を生かして増やすことも考えよう
電気代や燃料費などの高騰は、節約で抑えることも大切です。しかし、モノの値段が上がり続けてしまえば、節約だけでは対応しきれません。たとえば、100円で購入できた缶コーヒーが500円に値上がりした場合、買うことをやめてしまうかもしれません。
節約だけで解決しようとすると、モノの値上がりに追いつけなくなることも考えられます。そのため、無駄な支出を少なくするだけではなく、資本を増やすことも考えてみてはいかがでしょうか。節約は、使わないことによる現状維持のような感覚です。
使わなかったお金を増やす方法は、相場変動のあるものに投資すること。たとえば、100円で購入できた缶コーヒーが500円で売れれば400円の利益を生み出します。
これは、あくまで例ですが、そのような売買益が期待できる株取引は、資産運用の手段のひとつです。ただし、株取引などは得もすれば損もあり得ます。そのため、専門知識や経験が必要です。中には、専門知識や経験がなくても専門家の判断で金融商品に投資する投資信託のような商品もあります。節約以外の取り組みとして、資産運用も考えてみてはいかがでしょうか。
【参考】
※1経済産業省資源エネルギー庁「電気料金の改定について(2023年6月実施)」
※2総務省統計局「年末年始の消費支出」
※3ENECHANGE株式会社「エネチェンジ|冬の平均的な電気代は?冬の電気代が高い理由と節約方法
※4消費者庁「消費者の意識からみるこれからの消費行動」
※5政府広報オンライン「節電をして電気代を節約しよう!手軽にできる節電方法とは?」
※6消費者庁「食品ロスを減らす!食品お片付け・お買い物マニュアル」