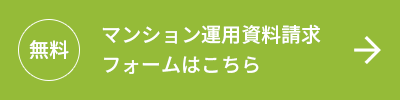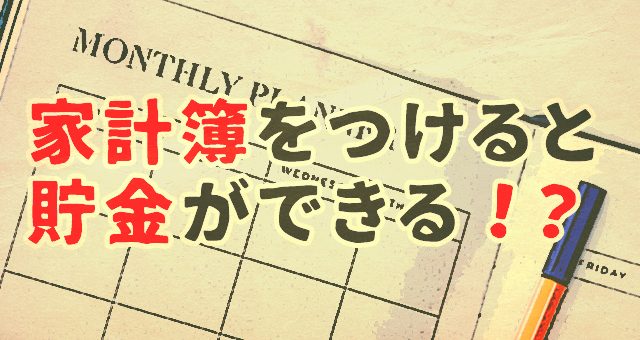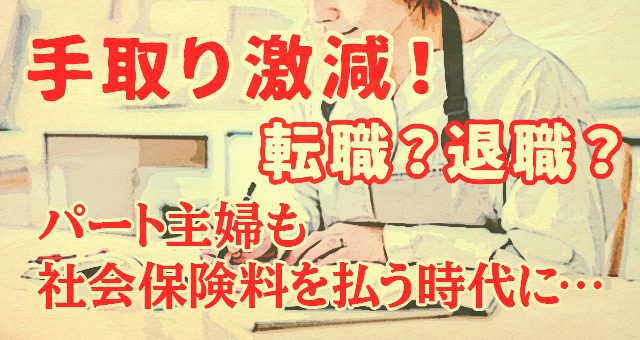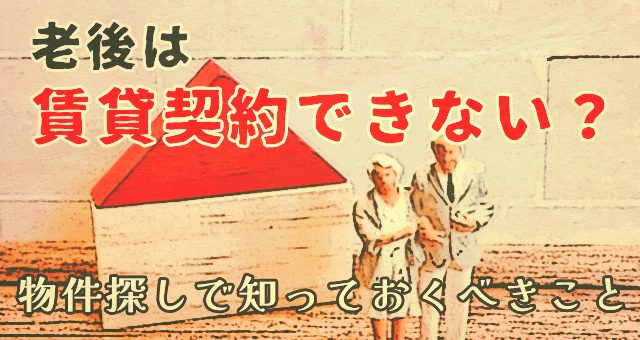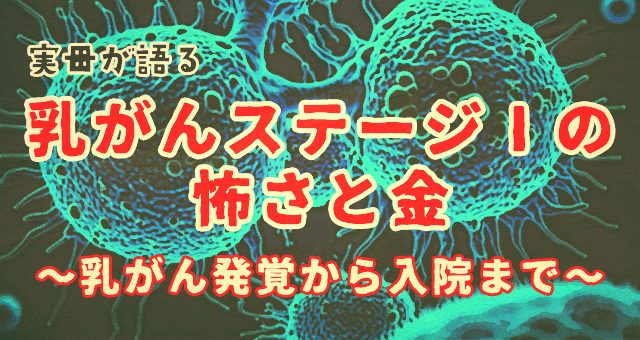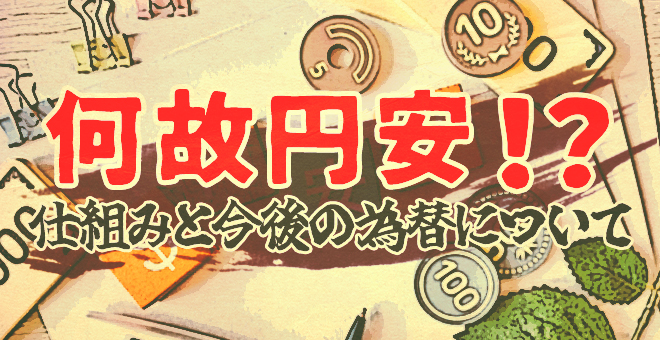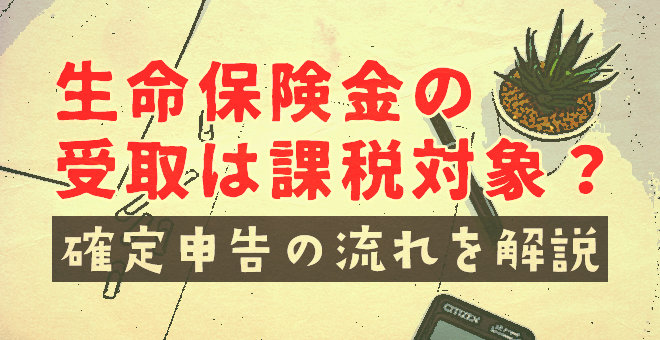ニトウコラム
みんなどんな方法で貯蓄してる?世代別の貯蓄方法を解説

金融商品には株式や投資信託、保険など多くの種類があります。「貯蓄を始めよう」と考えたとき、「種類が多すぎてどれで貯蓄すればいいのか分からない」と悩むこともあるかもしれません。本記事では、金融広報中央委員会が行った「令和4年(2022年) 家計の金融行動に関する世論調査」の結果から、多くの人が保有している金融商品について紹介します。ニーズ別の金融商品も紹介しますので、ぜひ貯蓄計画を立てる際に役立ててください。
目次
1.【世代別】みんなが選んだ貯蓄の方法とは?
金融広報中央委員会が行った「令和4年(2022年) 家計の金融行動に関する世論調査」では、現在保有している金融商品についての調査が行われました。ここでは、「単身世帯」と「2人以上世帯」に分けて、世代別の貯蓄の方法について見ていきましょう。
1-1.【単身世帯】若年層は投資信託での貯蓄が多い
まずは、単身世帯の貯蓄方法です。同調査による結果を下記の表にまとめました。
(単位:%、複数回答可)
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | |
| 預貯金 | 91.8 | 95.1 | 93.5 | 94.0 | 97.5 | 97.2 |
| 金銭信託 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 3.0 | 3.8 |
| 積立型保険商品 | 13.1 | 20.1 | 22.8 | 25.1 | 30.1 | 30.3 |
| 個人年金保険 | 10.9 | 19.1 | 17.6 | 21.9 | 21.0 | 18.9 |
| 債券 | 4.0 | 5.2 | 6.5 | 4.9 | 9.3 | 9.4 |
| 株式 | 17.5 | 25.9 | 26.2 | 20.5 | 26.0 | 34.1 |
| 投資信託 | 20.8 | 31.2 | 25.3 | 19.4 | 26.0 | 25.1 |
| 財形貯蓄 | 8.0 | 5.9 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 0.8 |
| その他 | 4.4 | 8.0 | 9.0 | 7.7 | 6.8 | 5.2 |
| 保有なし | 8.0 | 4.6 | 5.9 | 5.5 | 2.3 | 2.8 |
引用:金融広報中央委員会「令和4年(2022年) 家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査]」
20代、30代の若年層では、全体の2~3割の人が投資信託での貯蓄を行っています。リスクを取って運用できる期間が長いことから「積極的な運用をしたい」と考えている人が多いのかもしれません。
また、20代では積立型保険商品の割合が低いことも特徴です。20代で積立型保険商品を選んでいる人は13.1%に留まっており、特に単身世帯では「万が一の事態に備えたい」というニーズが少ないことがうかがえます。
1-2.【2人以上世帯】保険商品を活用した貯蓄が多い
次に、2人以上世帯の貯蓄方法について世代別に見ていきましょう。
(単位:%、複数回答可)
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | |
| 預貯金 | 94.2 | 95.8 | 96.5 | 96.5 | 97.7 | 98.2 |
| 金銭信託 | 10.5 | 6.9 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 3.8 |
| 積立型保険商品 | 31.6 | 37.5 | 34.7 | 37.5 | 37.3 | 37.1 |
| 個人年金保険 | 22.2 | 25.3 | 24.2 | 31.0 | 26.9 | 19.2 |
| 債券 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 10.3 | 9.0 |
| 株式 | 22.2 | 28.5 | 28.4 | 31.4 | 36.0 | 39.8 |
| 投資信託 | 22.2 | 29.8 | 27.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| 財形貯蓄 | 8.8 | 13.4 | 11.4 | 15.4 | 5.5 | 3.6 |
| その他 | 5.3 | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 7.1 | 6.6 |
| 保有なし | 4.7 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 1.3 |
引用:金融広報中央委員会「令和4年(2022年) 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]」
2人以上世帯になると、単身世帯とは貯蓄の方法に大きな違いが見られます。20代~60代では積立型保険商品の割合が最も多くなっており、「万が一の事態に備えたい」というニーズがより強いことが分かります。
また、個人年金保険の割合も単身世帯に比べて多くなっており、保険を活用した貯蓄が主流のようです。
2.【世代別】比重を置いている金融商品は何?
ここまで、各世帯でさまざまな金融商品を取り入れながら貯蓄を行っていることが分かりました。では、金融資産のうち最も比重を置いている金融商品はどれなのでしょうか。
本調査では、種類別の金融資産保有額に関する調査も行われました。下記表は総世帯の調査結果を世代別にまとめたものです。
(単位:万円)
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | |
| 預貯金 | 162 | 327 | 469 | 672 | 1,038 | 947 |
| 上記のうち定期性預貯金 | 37 | 86 | 164 | 321 | 611 | 536 |
| 金銭信託 | 8 | 10 | 14 | 19 | 27 | 19 |
| 生命保険 | 19 | 72 | 125 | 220 | 249 | 245 |
| 損害保険 | 5 | 7 | 16 | 27 | 29 | 34 |
| 個人年金保険 | 19 | 36 | 65 | 143 | 161 | 91 |
| 債券 | 12 | 7 | 36 | 25 | 100 | 129 |
| 株式 | 37 | 131 | 215 | 360 | 366 | 536 |
| 投資信託 | 26 | 88 | 104 | 134 | 197 | 221 |
| 財形貯蓄 | 22 | 18 | 52 | 70 | 18 | 9 |
| その他 | 5 | 14 | 18 | 35 | 32 | 26 |
引用:金融広報中央委員会「令和4年(2022年) 家計の金融行動に関する世論調査[総世帯調査]」
各世代ともに、預貯金に最も多くの資産を置いていることが分かりました。株式や投資信託による資産運用が広く浸透してきたものの、「まとまった現金を持っておきたい」という考えの人がどの世代にも多いようです。
日本銀行の「資金循環の日米欧比較」によると、米国の家計における現金・預金比率は13.7%となっているため、日本の家庭の貯蓄は米国に比べてかなり現金比率が高いことが分かります。
3.【ニーズ別】おすすめの金融商品を紹介
金融商品にはそれぞれ特徴があり、自分の投資意向やライフプランに適したものを選ぶ必要があります。ここからは、ニーズ別のおすすめ金融商品を紹介していきます。
3-1.万が一のための備えをしたい人は【保険商品】
これからの人生を考えると、「もしケガや病気で働けなくなったらどうしよう」、「自分に何かあったとき、子供の教育資金が心配」など、さまざまな不安が浮かびます。万が一の事態にしっかりと備えておきたい人は保険商品がおすすめです。
ひとくちに「保険」といっても多くの種類があり、「どの保険に入ればよいのだろう」と悩むこともあるかもしれません。ここでは、代表的な保険商品の種類を紹介します。
| ・ケガや病気で働けなくなった場合に備える ⇒ 就業不能保険
・自分が亡くなった後の家族の生活資金に備える ⇒ 生命保険 ・病気にかかる医療費に備える ⇒ 医療保険・がん保険 ・老後の生活資金に備える ⇒ 個人年金保険 ・子供の教育資金に備える ⇒ 学資保険 |
生命保険には保障が一生続く「終身保険」の他に、保険期間を終えたら満期保険金を受け取れる「養老保険」もあります。「現役を終えたら死亡保障は最低限でいい」という人は、老後資金の備えにもなる養老保険を検討してみるとよいでしょう。
3-2.リスクを取って運用したい人は【株式】
個別銘柄の株式投資は、投資信託や債券での運用に比べてリスクが高くなる傾向にあります。ただし、中には株式優待や配当が受けられるものもあり、貯蓄の一環として取り組む人も多く見られます。
長期的な資産形成を考えるのであれば、デイトレードのように短期売買を繰り返す形ではなく、長い目で成長期待が持てる銘柄へ投資をしましょう。
また、株式投資は一般NISAが利用できることも特徴です。一般NISAは上場株式が対象となっており、日本株式だけでなく米国株式などの外国株式にも非課税で投資できます。
2024年以降の新NISAでも「成長投資枠」で上場株式の投資が行えますので、上手く資産形成に活用しましょう。
3-3.手軽に分散投資をしたい人は【投資信託】
投資信託とは、投資家から集めたお金をもとに「ファンドマネージャー」と呼ばれる人が銘柄選定をしながら運用を行う金融商品です。1つのファンドを購入するだけで複数の銘柄に分散投資できるため、「投資に手間をかけたくない」、「どんな銘柄に分散投資すればいいのか分からない」という人に向いています。
また、投資信託は少額から始められることも特徴です。証券会社によっては100円から購入できるところもあるため、「いきなり大きな金額を投資するのは怖い」という人は少額投資から始めてみるとよいでしょう。
なお、投資信託も株式投資と同様にNISA制度の対象です。2024年以降は制度が恒久化されることも決まっているので、長期的な資産形成も可能となります。ぜひ非課税制度を活用しながら貯蓄に役立てましょう。
3-4.手堅く運用をしたい人は【債券】
債券は国や地方公共団体が発行する「公共債」の他に、企業が発行する「社債」があります。株式に比べるとリスクが低減されるため、「リスクを抑えて運用したい」「大きなリターンは望んでいない」という人に向いている金融商品です。
また、株式と債券の大きな違いに、「満期が決まっている」ということが挙げられます。債券はあらかじめ満期が決まっており、満期を迎えると投資家へお金が戻される仕組みです。債券を保有している間は利子を受け取れるので、満期までの利回りを想定しやすいこともメリットといえます。
「〇年後にお金を使う予定があるので、それまで安定的な運用をしたい」という人は、債券投資を検討してみましょう。
3-5.生活防衛資金は【預金】
株式や投資信託で利回りを得ることも大切ですが、生活防衛資金は預金に確保しておく必要があります。
急な出費でお金が必要となったとき、株式や投資信託は現金化するのに数営業日かかってしまいます。また、市場の動向によっては、損失が出ていることもあるかもしれません。株式や投資信託などの金融商品は生活に必要なお金ではなく、あくまで余裕資金で投資するようにしましょう。
生活防衛資金の目安は、生活費の3ヶ月~半年程度だといわれています。仮に1ヶ月の生活費が20万円だとすると、60万~120万円は普通預金や定期預金に預けて、いつでも引き出せるようにしておくと安心です。
4.まとめ
貯蓄の方法には株式や投資信託、保険などさまざまな種類がありますが、どの金融商品を選ぶかは年代やライフプランによっても異なります。まずは、「何のために貯蓄を行うのか」という目標を明確にすることが大切です。貯蓄の目標がはっきりすれば、自ずと選ぶべき金融商品も絞れるようになるでしょう。
【参考】